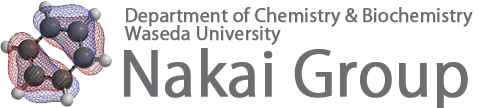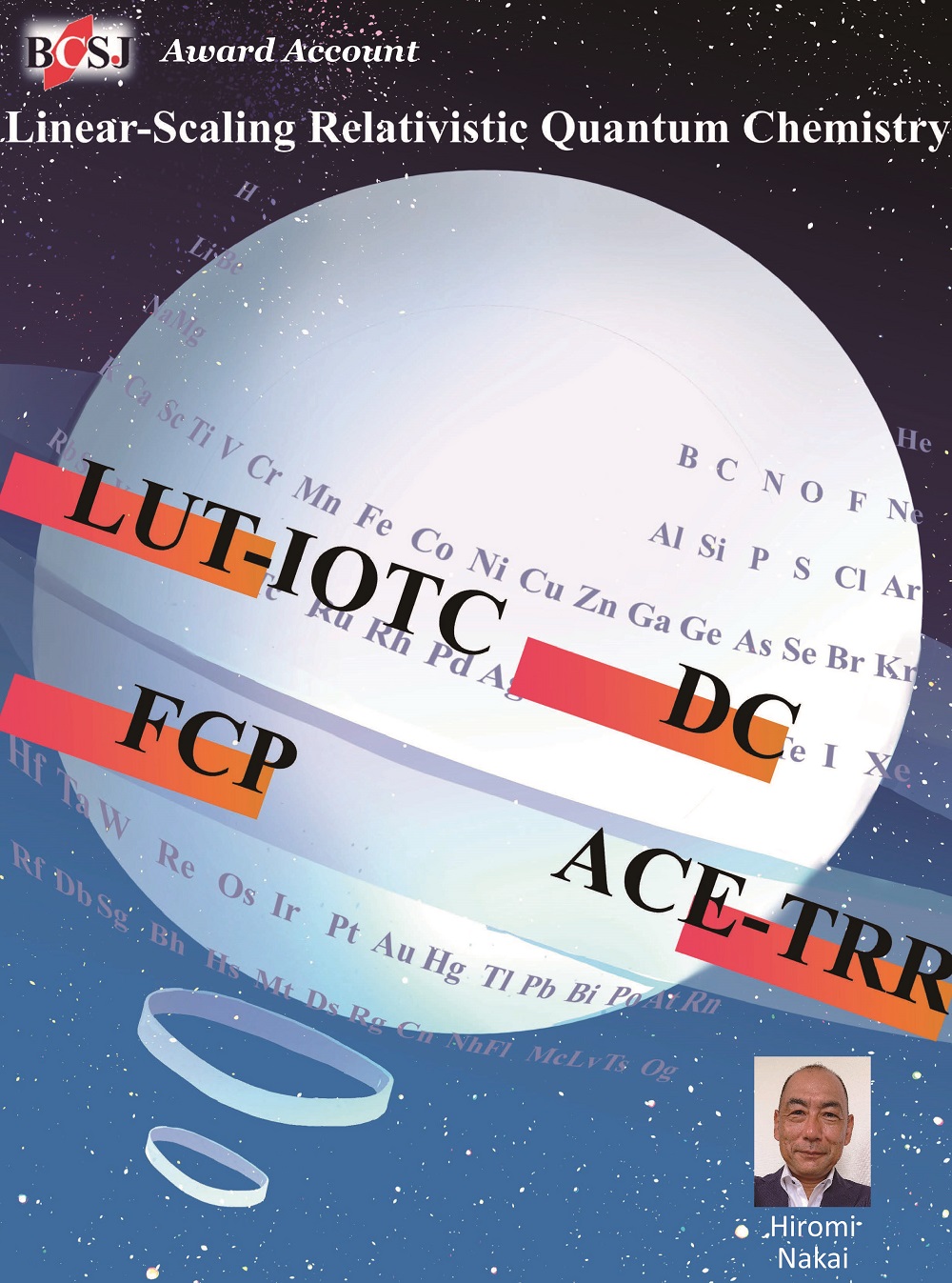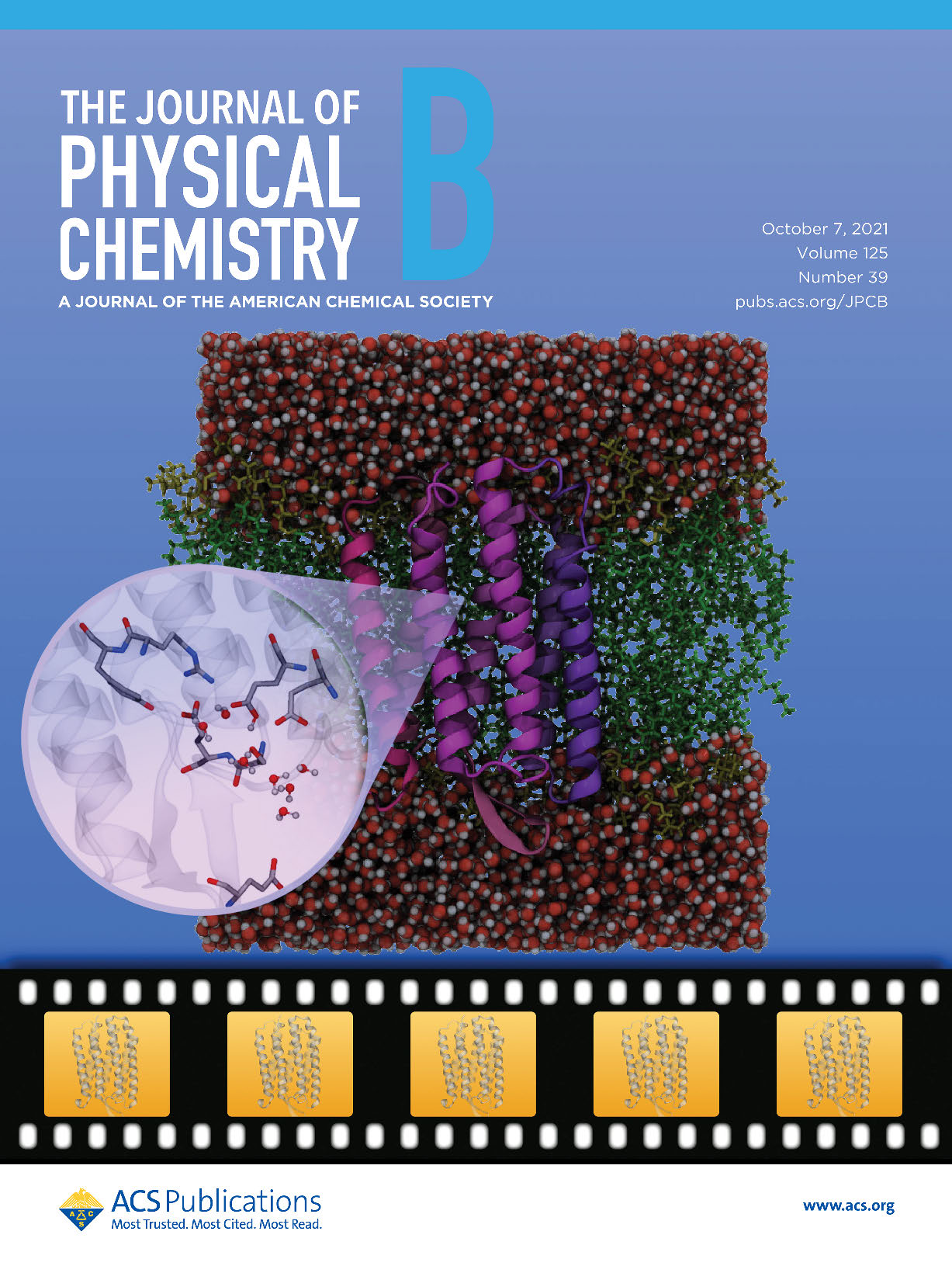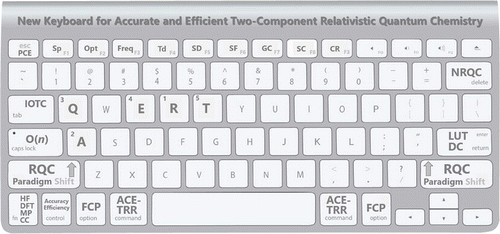中井教授が世話人を務める第11回量子化学スクールが11月30日、12月1日にオンライン開催されます。
中井研究室からは、藤波助教がトピックス「機械学習」について講義を行います。
<プログラム>
11月30日(火)
司会:藤田貴敏
9:00 – 9:10 開会の挨拶 中井浩巳(早稲田大学)
9:10 – 10:40 小林 正人 先生(北海道大学)
「Hartree-Fock(-Roothaan)法: 理論概要から詳細、数値結果まで」
10:50 – 12:20 中谷 直輝 先生(東京都立大学)
「電子相関とpost-HF法」
司会:清野淳司
14:00 – 15:30 神谷 宗明 先生(岐阜大学)
「密度汎関数理論の基礎」
15:40 – 17:10 福田 良一 先生(京都大学)
「電子励起状態の計算化学」
司会:清野淳司
17:30 – 18:30 交流会
12月1日(水)
司会:藤田貴敏
9:00 – 10:30 岸 亮平 先生(大阪大学)
「量子化学に基づく分子物性の予測と解釈」
10:40 – 12:10 和佐田 祐子 先生(名古屋工業大学)
「GaussianによるSCFおよび構造最適化計算の実際」
司会:藤田貴敏
14:00 – 15:30 水上 渉 先生 (大阪大学)
「量子コンピュータを用いた量子化学計算の基礎」
15:40 – 17:10 藤波 美起登 先生 (早稲田大学)
「機械学習の基礎と実践のためのヒント」
17:10 – 17:20 閉会の挨拶 江原正博(分子研)
——————–
<終了報告>
参加登録者が過去最高の470名超であり、実際の参加者も最高300名弱という大変盛況な会となりました。