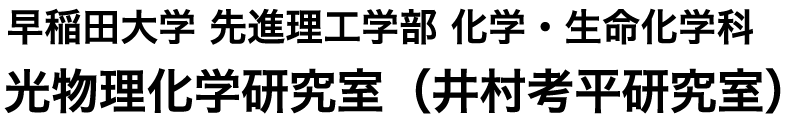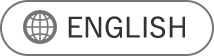研究内容
概要
ナノテクノロジー,ナノサイエンスの進展とともに,ナノ物質のナノ空間スケールでの物性評価が重要となってきています。光の吸収,反射,散乱などを測定する分光法は,幅広いエネルギー領域で物質の物性評価を可能とします。しかしその一方で,空間分解能は光の回折現象のために光の波長(可視光で数百ナノメートル)程度に制限されています。近年,近接場光学という新しい原理に基づく光学顕微鏡が開発され,光の回折限界を超えるナノスケールの空間分解能を実現することが可能となっています。
ナノ物質の中でも貴金属などのナノ微粒子は,特異な光学特性を示すことから近年特に注目を浴びています。例えば,金の場合,バルク状態では金色ですが,サイズがナノスケールになると鮮やかな呈色を示すようになります。ステンドグラスの赤色は,金微粒子の光学特性に起因します。貴金属微粒子の光学特性は,プラズモン共鳴と呼ばれる自由電子の集団電子振動に起因しています。このプラズモンの空間スケールは,光の波長と比べて小さいために通常観測することはできません。近接場光学顕微鏡を用いることでプラズモンの空間構造(波動関数)を可視化することが可能となります。
プラズモンは,光の閉じ込めや光電場の増強効果を誘起することから,光エネルギー利用(光電変換,光熱変換),高感度化学センサー,電子材料,医療応用などにおいて極めて有望です。プラズモンの機能を理解しこれを応用していくためには,その波動関数を理解することが本質的です。プラズモンは,応用面だけでなく基礎科学の分野においても新しい原理や現象を探求する媒介として注目することができます。
研究テーマ
- ナノ顕微分光イメージング手法の開発
- プラズモンの可視化と制御
- 金属ナノ物質を用いた高感度センシング
- 炭素ナノ材料の創成と光学応答制御
- 光キラル場制御と結晶化への応用
- 二次元ナノ物質の光学特性の解明
- ナノ物質を用いた光操作とレーザー発振
実験装置
測定装置
- 近接場光学顕微鏡,走査型電子顕微鏡,光学顕微鏡,高感度分光システム
- 超短パルスレーザーシステム (20 fs, 100 fs),連続発振レーザー,キセノンランプ
- 可視紫外分光光度計,蛍光分光光度計
- 真空蒸着装置,有機合成装置
最近の研究プロジェクト
- 科学研究費補助金 学術変革領域研究(A)「光の螺旋性が拓くキラル物質科学の変革」(R4-R9)
代表 井村考平
「超螺旋光によるナノキラル光場の創成とその可視化」
- 科学研究費補助金 基盤研究B(R5-R8)
代表 井村考平
「光場制御と強結合によるナノ光増強場の高度化と機能開拓」
- 科学研究費補助金 挑戦的研究(萌芽)(R4-R5)
代表 井村考平
「空間選択的化学反応を用いた機能性ナノ物質の創成と光特性制御」
- 科学技術振興機構 未来社会創造事業(2021-)
「低侵襲ハイスループット光濃縮システムの開発」
代表 飯田琢也(大阪公立大学)
「ナノ顕微分光計測による光濃縮基板の局所物性評価」
共同研究者 井村考平
- 科学研究費補助金 基盤研究B(R2-R5)
代表 井村考平
「光場操作によるナノ物質の光励起状態とエネルギー伝達の制御」
物質機能とエネルギー伝達を精緻に制御することは,科学技術における究極的な課題の一つである。この目標 を達成するためには,従来の光と物質の相互作用の枠組みを超える新しい原理に基づく光特性制御法の構築が不 可欠である。サブ波長スケールのナノ物質は,光を空間的・時間的に閉じ込めて局在増強光場を発生する。この 局在光場と物質の相互作用は,新しい光学選択則,光増強磁場-物質相互作用,多極子状態の生成を通して,新しい励起状態を誘起することが可能である。しかし,これらを積極的に活用した例は限定的であり,その学術的 追求は大きな課題となっている。本研究では,励起光場の空間と偏光ベクトルの操作により,物質の光励起状態 とエネルギー伝達の制御を実現し,物理化学に新しい学理を構築することを目標とする。本研究により,光と物 質の相互作用の活用に新しい展開が可能となり,これを基軸とした学術分野に大きな波及効果が期待される。
過去の研究プロジェクト
- 科学研究費補助金 挑戦的研究(萌芽)(R2-R3)
代表 井村考平
「メソ物質における電気磁気双極子遷移の可視化と光学特性制御への応用」
光(電磁場)と通常の物質の相互作用において光磁場の影響は無視できる。しかしメソ物質では,光磁場が増強 され光磁場と物質の相互作用が著しく増大する。この現象を理解し操作することで,メソ物質の特性を自在に制 御できる可能性がある。本研究では,物質内の光電場と光磁場を可視化し,光特性制御のための機構解明を目指 す。本研究により得られる成果は,化学分野をはじめ光回路や光ナノデバイスなど幅広い分野への波及効果が期 待される。 - 科学研究費補助金 基盤研究B(H28-H31)
代表 井村考平
「金属ナノ構造体における光励起状態の時空間コヒーレント制御と光伝播制御への応用」
金属ナノ構造体に光励起される自由電子の共鳴モードは,電子と光場が時間的また空間的に結合した光強結合状 態である。複数の光-電子結合モードを同時励起し,その重ね合わせ状態をコヒーレントに制御することで,光 強結合状態を時間と空間の両軸で制御することが可能である。本申請では,金属ナノ構造体に誘起される光励起 状態の時空間コヒーレント制御を実現し,光と熱の伝播制御法を構築することを目的とする。 - 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究(H28-H29)
代表 井村考平
「カソードルミネッセンス顕微分光装置の高度化」 - 科学研究費補助金 新学術領域研究「高次複合光応答分子システムの開拓と学理の構築」(H26-H30)
代表 井村考平
「メソ構造を利用した光化学反応の高次機能制御」
光の波長と同程度の大きさであるメソ構造体は,光アンテナ効果や遅延効果により光と強く相互作用するためバ ルク固体とは異なる性質を示す。メソ構造体の一つである貴金属ナノ構造体では,プラズモン(自由電子の協同 的な電子振動)励起により,ナノ空間への光の閉じ込めと増強を誘起するなど,光―物質間の強相互作用に起因 する極めて特異な性質を発現する。本研究では,メソ構造体に誘起される局在電場の近接場相互作用により,一 分子一光子応答を超える新規光応答制御スキームを構築し光化学反応,また分子の高次機能制御を実現すること を目標とする。 - 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究(H26-H27)
代表 井村考平
「近接場ナノ反射分光顕微鏡の開発」
近接場光学顕微鏡の発展により,ナノ物質の光学特性の実空間での計測が可能となっている。しかし近接場光学 顕微鏡は,原理上および動作上の問題から通常の顕微鏡において適用可能な分光手法が十分に取り入れられてい ない。例えば反射分光手法は,不透明な試料の分光観察を可能とする手法であるが,近接場光学顕微鏡ではこれ が実現されていない。ナノ構造体は,電子デバイスへの応用を見据えてしばしばシリコンなどの不透明基板上に 作製される。ナノ構造の特性を理解し応用するためには,その電子状態の評価が本質的に重要である。本研究で は,近接場光学手法と広い波長帯域で動作可能な変調分光法とを組み合わせて,反射スペクトル観察を可能とす る近接場ナノ分光顕微鏡を開発し,その有効性と汎用性を明らかにすることを目的とする。 - 科学研究費補助金 新学術領域研究「電磁メタマテリアル」(H25-H26)
代表 井村考平
「プラズモニックメタマテリアルのナノ分光研究」
メタマテリアルの構成要素であるプラズモンのモード間相互作用を実空間実時間で可視化し,相互作用がメタマテリアルの機能に及ぼす効果とその機構を解明することを目的とした。 周期的およびランダムに配置したナノ構造体を研究対象とし,プラズモンモード間の相互作用を近接場光学顕微鏡を用いて測定した。さら に,近接場光学顕微鏡とフェムト秒パルスレーザーとを組み合わせて,非線形計測,時間分解計測を行い,プラ ズモンモード間の相互作用ダイナミクスをフェムト秒の時間スケールで可視化した。プラズモンモード間の相互作用を時間と空間の両軸で研究し解明することを最終目標とした。 - 科学研究費補助金 基盤研究B(H24-H27)
代表 井村考平
「ナノ粒子集合体の光励起状態の可視化と制御」
光励起状態の波動関数を時間と空間の両軸で制御すれば,単一の分子であっても多様な特性を誘起することがで きる。しかし,光の集光限界は分子の空間スケールより遥かに大きく,分子の特定部位を空間選択的に光励起す ることはできない。ナノ粒子では,光との空間スケールのミスマッチが小さくなり,集光法を工夫するこ とで,粒子の特定部位を選択励起することができる。ナノ粒子の光励起状態は,電子状態の相互作用に関して, 原子軌道とのアナロジーが成立する。したがって,分子と同じ骨格構造をもつナノ粒子集合体では,光励起状態 が分子軌道と類似した空間特性をもつと期待される。本研究では,ナノ粒子集合体に誘起される光励起状態の可 視化とその時空間制御を実現し,多様な系に適用可能な光励起状態制御法の構築を目的とする。 - 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究(H24-H25)
代表 井村考平
「単一分子吸収分光装置の開発」
吸収分光法は,分子の同定に有効である一方で単分子感度を実現することは困難である。本研究では,光照射領域をナノメートル空間に制限することで,吸光度を大きくし分子の吸収分光測定を実現することを提案した。 光照射領域の制限法として開口型近接場プローブ内に発生する光場を利用することを提案し,これを自作して原理検証を行なった。本研究の結果,当初の予想通り照射領域の制限により吸光度の向上,つまり感度の向上を 実現し,微小なナノ物質の吸収スペクトル測定が可能となった。
共同研究者
国内
- 分子科学研究所
岡本裕巳教授 - 北海道大学
三澤弘明教授,上野貢生教授
- 大阪公立大学
飯田琢也教授,床波志保准教授 - 大阪公立大学
小畠誠也教授 - 大阪公立大学
細川千絵教授 - 名古屋大学
鳥本 司教授 - 関西学院大学
田和圭子教授
国外
- The University of Strathclyde
Dr. Francesco Papoff, Dr. Benjamine Hourahine